みなさん こんにちは
かずきです。
→最近は様々なことに対しての情報が多いですね。この時期になるとオープンキャンパスも終盤になり色々と考えていかなければならない時期になってきます。オープンキャンパスに行ったけど実際どんな進路を描いていこうかなとぼんやり思っている人も多いのではないでしょうか。高校生の進路を取り巻く環境というのが最近変わってきているのでその部分について説明してみます。
高校生の進路を取り巻く環境について
→高校生の進路は10年前に比べるとインターネットの発展や動画配信により情報を手に入れやすくなりました。時代とともに新しい職業(Youtuber, AIエンジニア, e-sportsなど)もできているので幅広くなってきています。なので、高校生の進路を取り巻く環境が変わってきていることについて語ります。
ネットの普及で進路の幅が広すぎる
→様々な人が情報を発信できる時代になったので本当に進路に関する情報や動画、職業に関する情報や動画がインターネット上には数多くあります。ところが、高校生からすると情報が多すぎてどの情報をどうすればいいのかやどのように検索したらいいのかが分かりにくくなっています。なので、かえってどの進路にすればいいのかが分かりにくくなってしまっています。
大学・短大、専門学校も学生の囲い込みで必死
→少子化の影響もあり、最近の大学・短大、専門学校って国公立でも私立でも人が来なければ経営にダメージを与え下手をすれば閉鎖になってしまう危険性があります。高校でもオープンキャンパスや大学・短大、専門学校のイベントに行きなさいという指導があったりもします。オープンキャンパスや大学・短大、専門学校のイベントって盛りだくさんあったりします。ところが、大学・短大、専門学校のイベントって営業的な要素が強いことがあります。場合によっては大学・短大、専門学校が主催にお金を払ってイベントをしていることもあって集客を目的にしているので実は進路選択が難しかったりします。イベントやオープンキャンパスがよくて実際に入学したけど後に違うというギャップを感じることもあります。
高校の先生も親は実はよく分かっていないことがある
→ご家庭によっては進路のことって意外にも分かっていないことがあります。その時に多いのが知名度思考になってしまうというパターンです。有名なところに行っておけば問題ないというパターンです。しかも、学校の先生が進路について知識が特定の部分に偏っていたり、分かっていないことが案外あるので学校の先生の指導も案外知名度思考になっていることがあります(もちろん、先生によります)。一部の私立高校は進学実績で学校のアピールをしている場合もあり学校の先生のお給料や査定にも直接影響したりすることもあります。
塾や予備校も進学実績のための指導になってしまう
→塾や予備校に聞けば進路指導ってしてもらえるのではと思う人も多いと思います。確かに塾や予備校は教科指導に対してはプロです。ただ、進路指導になると進学実績や入塾者を増やすために有名なところや偏差値の高いところになってしまうことがあります。意外にも大手の塾や予備校になればなるほど進学実績のための指導になっていることが多かったりします。今は少なくなってきてはいますが、本人の適性をあまり考えずに模試で偏差値が高いと難関国公立大学や医歯薬みたいな進路の指導をしている塾も実際にはあります。
どう進路選びをすればいいの?
→オープンキャンパスの裏側と進路選びの落とし穴があることは分かったのだが現実にはどのように進路選びをしていけばいいのかが分かりにくいと思うのでその部分について書いてみます。
情報を整理する力を身につけよう
→進路の情報はインターネットや動画も含め多すぎますが、すべての情報を追いかける必要はありません。まずは気になる分野を起点にネットで調べてみることが大切です。自分が興味を持てる分野や将来の働き方に関係する情報だけをピックアップするのもありです。ただ、そうは言っても実際に何がしたいのかやどう生きていきたいのかが分からない場合もあります。
自分の“軸”を決める
→学校の名前や偏差値よりも、「どんな環境で学びたいか」「卒業後にどう働きたいか」という軸を先に決めましょう。たとえば「海外で働きたい」「専門スキルを早く身につけたい」など、目的が決まれば情報も取捨選択しやすくなります。これを聞くと自分の“軸”が定まらない人も多いと思うのですが、軸が定まらない人はとりあえずの軸を決めるのが大切です。お勧めの記事は第三者の視点を活用する →学校や塾の先生、保護者以外にも、OB・OG、在学生から意見を聞くと、新しい発見があります。特に同じ学校や学科を卒業した先輩の話は、パンフレットには載っていないリアルな情報が得られます。逆に、学校の先生や塾の先生の話は半身半疑で聞き、あくまでも参考意見程度にとどめるのがおススメです。というのは、学校の先生(特に、進学重視の私学)や塾(特に進学塾)は進学実績重視で生徒を呼び込むための材料になっていることが多かったりします。 →インターネットやパンフレットの情報だけでは分からないことが多いです。学校見学、短期講習、ボランティア、アルバイトなど、実際にやってみることで進路選びの判断材料が増えます。 →進路選びは、どれだけ情報を集めても100%正解はありません。進路を決めた後に方向転換する人もたくさんいます。大学にってからでも編入・転入はありです。「この時点ではベスト」と思える選択をすることが大事で、柔軟に軌道修正できる姿勢が将来の安心につながります。 →進路選びには情報の多さや学校・塾の事情など落とし穴もあります。だからこそ「自分の軸」を持ち、体験や第三者の声を参考にしながら柔軟に考えることが大切です。完璧な答えはなくても、「今のベスト」を選ぶ姿勢が将来につながります。体験から判断する
「完璧な選択」はないと知る
まとめ
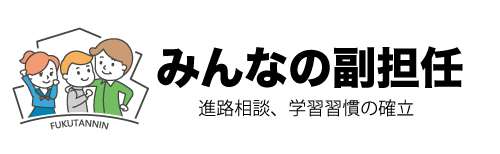

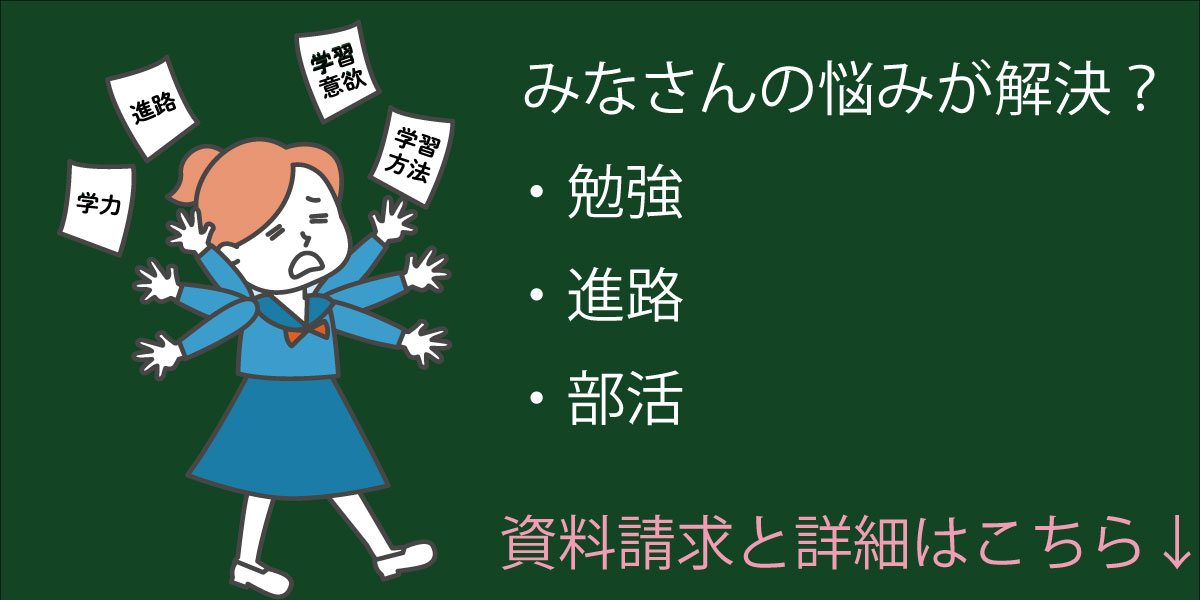
コメント